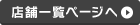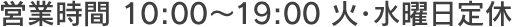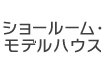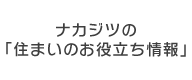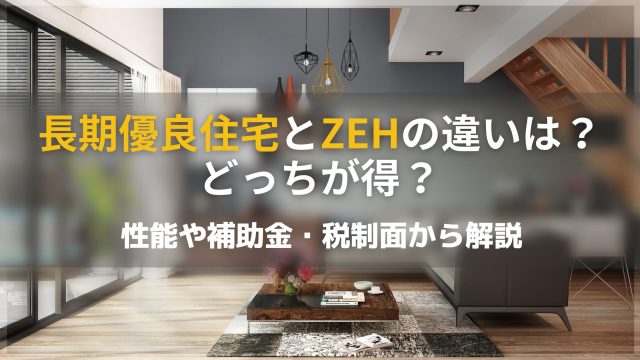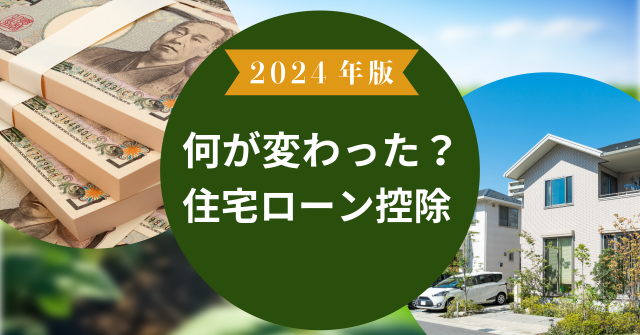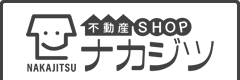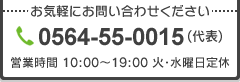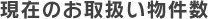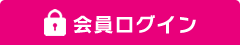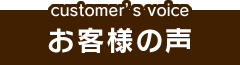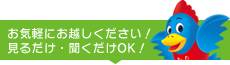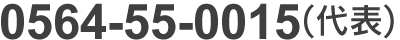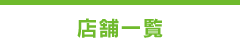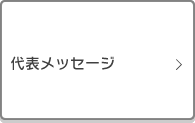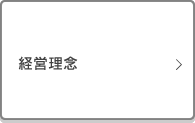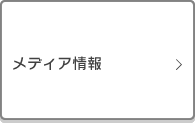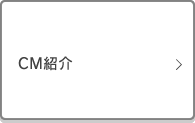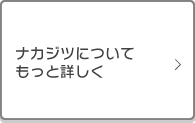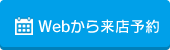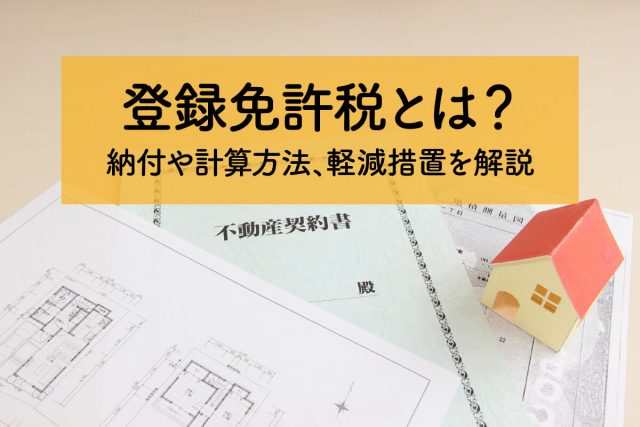
住宅取得する際には、税金を含めさまざまな諸費用がかかります。諸費用のうち登録免許税は、住宅取得時にかかる諸費用として、数十万円規模の支出となります。住宅を取得する際に初めて登録免許税について知る人もいらっしゃるでしょう。そこでこの記事では、登録免許税の基本をはじめ、税率や納付方法、具体的な計算方法などについて解説します。
目次
登録免許税とは?
建物や土地を取得したり、取得時に融資を受けたりする際に、当該不動産を法務局(登記所)に登録することを不動産登記といい、不動産の情報は一般公開され、誰でも閲覧することができます。不動産登記には次のような種類があります。
- 所有権の保存登記
建物を新築した場合などで、所有者の情報を登記する。なお所在地や床面積などの建物情報を登記することを表題登記という。 - 所有権の移転登記
土地や建物の所有者が、売買・相続・贈与などで変更したときに登記する。 - 抵当権の設定登記
住宅ローンを組んだ場合など、抵当権を設定するときに登記する。
表題登記を除き、不動産登記をする際に課税されるのが登録免許税です。また表題登記以外、登記は義務付けられていません(※)が、不動産の所有者や債権者を明確にするために登記をします。なお登録免許税は基本的に、不動産の売買において買主が負担します。
※相続登記は、2024年をめどに義務化される予定

登録免許税の納付方法
登録免許税は原則、現金による納付となります。金融機関(日本銀行歳入代理店)や税務署で納付し、領収証書を登記申請書に貼り付けて法務局に提出します。またオンライン申請の場合には、インターネットバンキング・モバイルバンキングやATMで納付(電子納付)することもできます。電子納付の場合も領収証書を法務局に提出します。
なお登録免許税額が30,000円以下の場合は、法務局で収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて提出することができます。納付方法の詳細につきましては、最寄りの法務局にご確認ください。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、不動産登記の種類と土地・建物によって、課税標準(登録免許税の基準となる金額)と税率が異なります。また税率が軽減される特例もあります。登録免許税額は次の式で求めます。
登録免許税 計算式
課税標準 × 税率
課税標準は不動産の価額となりますが、実務上は次の価額を用います。
登録免許税 課税標準
- 所有権の保存・移転登記:固定資産税評価額
※新築で固定資産税評価額がない場合は新築建物課税標準価格認定基準表に基づいて認定された価額 - 抵当権の設定:債権額(住宅ローンの借入金額)
固定資産税とは不動産保有時に課税される税金で、固定資産税評価額は固定資産税の基準となる金額です。固定資産税評価額は実勢価格の70%程度で、課税明細書などで確認できます。
次におもな登録免許税の税率などをまとめます。
<登録免許税 税率>
| 税率 | 軽減税率 | |
| 所有権の保存 | 0.4% | - |
| 所有権の移転(売買) | 2.0% | 1.5% |
| 抵当権の設定 | 0.4% | - |
※軽減税率は、令和8年3月31日の登記まで
※出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
| 税率 | 軽減税率 (一般住宅) |
認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | |
| 所有権の保存 | 0.4% | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
| 所有権の移転(売買) | 2.0% | 0.3% | マンション等0.1% 戸建て0.2% |
|
| 抵当権の設定 | 0.4% | 0.1% | ||
※軽減税率は、令和6年3月31日までなど所定の要件がある。(令和4年税制改正で2年延長)
※出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
表の通り、住宅の登記では認定長期優良住宅、認定低炭素住宅では所有権の保存登記、移転登記がさらに軽減されます。
登録免許税額の具体的な計算方法
では実際に登録免許税としてどのくらい支払わなければならないか、具体的に計算しながら新築住宅の場合と中古住宅の場合で確認します。

【ケース1】住宅を新築した場合
住宅を新築する場合、土地は不動産販売会社からの所有権移転登記、建物は所有権の保存登記となります。また住宅ローンを利用すれば抵当権の設定登記をします。建物は新築ですので、新築建物課税標準価格認定基準表に基づいて課税標準が決定されます。課税標準を、土地2,000万円、建物2,000万円、債権額4,000万円として登録免許税額(軽減税率適用後)を計算します。
・土地の所有権移転登記
2,000万円 × 1.5% = 300,000円
・建物の所有権保存登記
2,000万円 × 0.15% = 30,000円
・抵当権の設定登記
4,000万円 × 0.1% = 40,000円
【ケース1】の場合、登録免許税の合計額は37万円となります。
【ケース2】中古住宅を購入した場合
中古住宅を購入した場合、土地・建物ともに所有権の移転登記となります。また住宅ローンを利用すれば抵当権の設定登記が必要です。土地2,000万円、建物1,000万円、債権額3,000万円として登録免許税額(軽減税率適用後)を計算します。
・土地の所有権移転登記
2,000万円 × 1.5% = 300,000円
・建物の所有権移転登記
1,000万円 × 0.3% = 30,000円
・抵当権の設定登記
3,000万円 × 0.1% = 30,000円
【ケース2】の場合、登録免許税の合計額は33万円となります。建物について所有権の保存登記と移転登記を比べると、移転登記の税率のほうが高いため、登録免許税額は高めに算出されます。なお不動産登記に関連して、登記を司法書士に依頼した場合は、登録免許税と合わせて司法書士への報酬が必要となります。
登録免許税が軽減される条件
登録免許税の税率のうち、住宅の登記(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)では、所定の要件を満たすと、軽減税率が適用されます。ここでは軽減税率の要件をまとめます。なお土地の所有権移転登記について、令和8年3月31日の登記までであれば軽減税率で税額計算します。
| 登記の種類 | おもな要件 |
| 所有権の保存登記 |
|
| 所有権の移転登記(新築住宅) |
|
| 所有権の移転登記(中古住宅) |
|
| 抵当権の設定登記 |
※中古住宅の場合は、 |
※「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」のいずれかの書類を提出する。
※出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
堺市「登録免許税の軽減要件
※令和6年3月31日の登記まで
一般的に住宅ローンを利用すれば、金融機関を通して融資時に登記をしますので、「新築または取得後1年以内の登記」の要件を満たすでしょう。軽減税率の適用をお考えの場合は、住宅探しの段階から「床面積50㎡以上」(中古住宅なら「取得日以前20年以内(鉄骨造などは25年以内)の建物」も)の要件を満たすことを確認しておきましょう。
また上記の要件のほか、手続き上の要件もあります。登記申請する際に、住宅がある市町村等の証明書を添付する必要があります。登記後に証明書を提出しても軽減税率を適用できませんので、注意が必要です。
一般住宅の軽減税率からさらに免税される認定長期優良住宅については別記事に詳しくまとめていますので、どのようなものか興味がある方はぜひご覧ください。
登録免許税をはじめとした諸費用なども含め住宅取得計画を
登記免許税も住宅取得に係る諸費用の一つで、住宅ローンと一緒に諸費用ローンを利用して準備することもできますが、利息がかかります。事前に登録免許税額の目安を知っておけば、頭金として準備するかローンを組むかの選択ができますので、早めに確認しておくとよいでしょう。
また取得する住宅の価格が高くなるほど納付する登録免許税も増えます。住宅取得時には不動産取得税や登録免許税、住宅保有時には固定資産税がかかります。取得時の諸費用だけでなく、入居後の支出も考えて住宅取得計画を立てることをおすすめします。
ナカジツでは資金計画からご相談お受けしております!
おうちを買いたい、買い替えたい!でも、どこから準備したらいいの?はじめてのマイホーム探しはわからないことだらけです。
不動産SHOPナカジツではライフスタイルをヒアリングし資金計画からサポートいたします。予算のなかで”自己ベスト”の、おうち探しを一緒にしていきましょう。